| HOME / 簡易レファレンス / サイデリアル星座帯 |
簡易レファレンス
サイデリアル星座帯
●トロピカル星座帯とサイデリアル星座帯とのズレ
西洋占星術で使用されている星座帯の位置は、毎年の春分点を牡羊座の起点(0度)としています。つまり、春分になった瞬間に太陽の位置する地点が牡羊座の0度となります。例えば、毎年3月21日の春分点から約1ヶ月間は牡羊座生まれ、次の1ヶ月間は牡牛座生まれ、その次の1ヶ月間は双子座生まれ・・・、という具合になります。
このトロピカル星座帯もかつては恒星を基準とする実際の星座の位置とほぼ対応していました(ここで、「ほぼ」と言っているのは厳密には天空上の実際の星座は等しく30度ずつには分割されていないためです)。しかし、地球の歳差運動のために、毎年少しずつ(およそ72年に1度ずつの割合で)星座の位置が逆行し、現在では実際のそれよりもおよそ24度近くズレているとされています。つまり、現在の春分点(=トロピカル星座帯での牡羊座0度)は、実際の恒星を基準とする牡羊座0度ではなく、実際には魚座6度付近にあることになります。
この移動する星座帯をトロピカル星座帯(移動星座帯)と呼び、恒星を基準として、移動しない星座帯をサイデリアル星座帯(固定星座帯)と呼んで区別しています。西洋占星術では、トロピカル星座帯を使用しますが、インド占星術ではサイデリアル星座帯を使用しています。この点が、インド占星術で使用する星座帯と西洋占星術で使用する星座帯の大きな相違点になります。そしてトロピカル星座帯とサイデリアル星座帯の差異、すなわちおよそ24度を現在におけるアヤナームシャ(Ayanamsa)と呼んでいます。
よって、ある時点におけるトロピカル星座帯とサイデリアル星座帯の関係は、その時点におけるアヤナームシャを介して以下の式で表わされます。
[トロピカル星座帯での度数]−[アヤナームシャ]=[サイデリアル星座帯での度数]
トロピカル星座帯からサイデリアル星座帯への変換あるいはその逆の変換は、いたって容易であることがわかります。

重要なアヤナームシャの選択
しかし、問題はアヤナームシャの精度にあります。かつて、トロピカル星座帯とサイデリアル星座帯は一致していたと言いましたが、それは紀元200年から600年頃と考えられ、実に400年もの幅があります。その理由は、春分点が牡羊座0度にあった時期がいつであったかに関して専門家の間で意見が分かれているためです。71.61〜71.67年に1度ずつトロピカル星座帯とサイデリアル星座帯の間にズレが生じるので(これもどの時期を指すかにより、あるいは専門家により若干異なりますが、違いの影響は無視できる程度に小さい)、例えば71.67年に1度ずつズレが生じているとして1970年におけるズレを計算すると、これまでの1370〜1770年間に19.1〜24.7度のズレが生じたことになります。つまり、1970年におけるアヤナームシャは平均して21.9度となりますが、最大値と最小値の間に実に5度近くの幅が生じることになります。
これまでに様々な占星家によってアヤナームシャが提案されていますが、インド占星家でもっともポピュラーなのはインド政府の暦改革委員長(Secretary of Calendar Reform Committee)のラヒリ(Lahiri)が考案したアヤナームシャです。その他、クリシュナムルティ(Krishnamurti)、ラーマン(B.V.Raman)、ファーガン=ブラッドリー(Fagan/Bradley)、リチャード・フック(Richard Hook)などによるアヤナームシャなど数十種類が存在しています。西洋占星家の間では、ファーガン=ブラッドリーのアヤナームシャが多用されているようですが、惑星サイクル(ダシャー・システム)を使用して予測をする場合はほとんど役に立たちません。彼らのアヤナームシャを使ってインド占星術の勉強をした場合、「インド占星術は全く当たらない」と感じてしまうかもしれません。ラーマンのアヤナームシャについても同様のことがいえます。実はこのアヤナームシャの選択こそがインド占星術の学習における大きな分かれ道といって差し支えないと思います。アヤナームシャが間違っていると、惑星期間(ダシャー)も正確でなくなりますし、分割図も使用できなくなります。その結果、「インド占星術は使えない」という結論に達してしまうのです。
東西占星術研究所では経験的に、ラヒリのアヤナームシャは精度が高いと認識しています。クリシュナムルティ教授のアヤナームシャ、「死の占星術(Astrology of Death)」の著者として有名なリチャード・フックのアヤナームシャも、ラヒリに非常に近いので、彼らのアヤナームシャで代替しても大きな違いは無いでしょう。
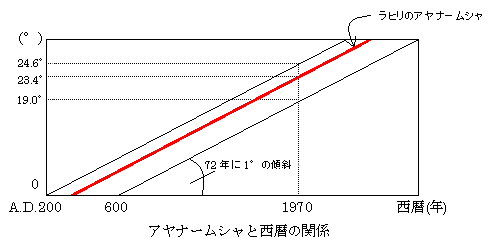
| 1970年1月1日におけるアヤナームシャ | |
| ラヒリ(インド政府公認) | 23度26分21秒 |
| ラーマン | 21度59分35秒 |
| ファーガン=ブラッドリー | 24度19分21秒 |
| クリシュナムルティ | 23度20分51秒 |
| リチャード・フック | 23度21分11秒 |
| ラヒリ・アヤナームシャ (1900年〜2001年) | ||
| 年 度 分 秒 | 年 度 分 秒 | 年 度 分 秒 |
1900 22 27 56
1901 22 28 44
1902 22 29 31
1903 22 30 16
1904 22 31 00
1905 22 31 43
1906 22 32 28
1907 22 33 14
1908 22 34 03
1909 22 34 54
1910 22 35 45
1911 22 36 38
1912 22 37 33
1913 22 38 28
1914 22 39 24
1915 22 40 20
1916 22 41 15
1917 22 42 09
1918 22 43 00
1919 22 43 49
1920 22 44 37
1921 22 45 22
1922 22 46 07
1923 22 46 52
1924 22 47 36
1925 22 48 22
1926 22 49 09
1927 22 49 57
1928 22 50 48
1929 22 51 40
1930 22 52 34
1931 22 53 30
1932 22 54 26
1933 22 55 21
|
1934 22 56 17
1935 22 57 11
1936 22 58 03
1937 22 58 54
1938 22 59 43
1939 23 00 30
1940 23 01 17
1941 23 02 02
1942 23 02 47
1943 23 03 30
1944 23 04 16
1945 23 05 03
1946 23 05 53
1947 23 06 44
1948 23 07 37
1949 23 08 32
1950 23 09 28
1951 23 10 24
1952 23 11 19
1953 23 12 14
1954 23 13 08
1955 23 14 00
1956 23 14 49
1957 23 15 38
1958 23 16 24
1959 23 17 09
1960 23 17 54
1961 23 18 38
1962 23 19 23
1963 23 20 10
1964 23 20 58
1965 23 21 48
1966 23 22 40
1967 23 23 34
|
1968 23 24 29
1969 23 25 25
1970 23 26 21
1971 23 27 17
1972 23 28 11
1973 23 29 04
1974 23 29 55
1975 23 30 44
1976 23 31 31
1977 23 32 17
1978 23 33 02
1979 23 33 47
1980 23 34 31
1981 23 35 17
1982 23 36 04
1983 23 36 53
1984 23 37 44
1985 23 38 37
1986 23 39 32
1987 23 40 28
1988 23 41 23
1989 23 42 19
1990 23 43 14
1991 23 44 08
1992 23 45 00
1993 23 45 51
1994 23 46 40
1995 23 47 26
1996 23 48 11
1997 23 49 56
1998 23 49 41
1999 23 50 25
2000 23 51 11
2001 23 51 59
|

![]()
![]() HOME
HOME
![]() ご案内
ご案内
![]() お知らせ
お知らせ
![]() 談話室
談話室
![]() 東西占星術ノート
東西占星術ノート
インド占星術![]() 簡易レファレンス
簡易レファレンス
![]() 検証 占星術
検証 占星術
![]() 研究日誌
研究日誌
西洋占星術 ![]() 検証 占星術
検証 占星術
特別寄稿![]() インド思想
インド思想
![]() 運命学
運命学
![]() 開運術
開運術
鑑定案内 ![]() 鑑定案内
鑑定案内
講座案内 ![]() インド占星術通信講座
インド占星術通信講座
![]() インド占星術公開講座
インド占星術公開講座
![]() インド占星術個人指導
インド占星術個人指導
![]() インド占星術テキスト
インド占星術テキスト
![]() 受講生の広場
受講生の広場
etc. ![]() リンク
リンク
![]() おすすめ書籍
おすすめ書籍
![]() 誕生日データベース
誕生日データベース
![]() サイデリアル・エフェメリス
サイデリアル・エフェメリス
![]() サイデリアル星座移動表
サイデリアル星座移動表
![]() 緯度経度検索サービス
緯度経度検索サービス
![]() ホロスコープ・プレゼント
ホロスコープ・プレゼント